塩と高血圧の話
柴田 真吾
(苫小牧市医師会・柴田内科循環器科)
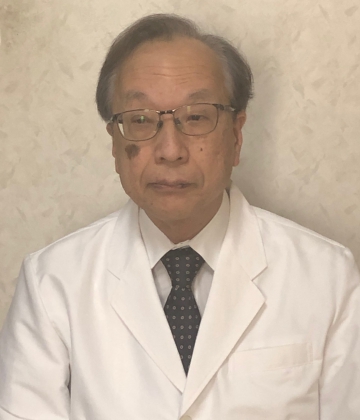
柴田 真吾
(苫小牧市医師会・柴田内科循環器科)
5月17日は「高血圧の日」、さらに毎月17日は「減塩の日」と制定されています。高血圧治療に減塩が必要なことは多くの方が知っています。 ところで、①理由は何でしょか?②また、分かっていても減塩が難しいのはなぜでしょうか?
①高血圧には、減塩で血圧が下降しやすいタイプ(食塩感受性高血圧)と、そうでないタイプ(食塩非感受性高血圧)とがあります。
前者の食塩感受性では、「塩分過多がひきがねとなり、腎臓でナトリウムが再吸収されることで、高血圧になる」と考えられており、後者の食塩非感受性では「血管収縮」が発症の主因と考えられています。食塩感受性の方は、高血圧の親がいる、肥満、中高年、腎機能の低下、外食の多い方にみられ、日本人の約4割にあたるという報告があります。
減塩が効果的な方は、感受性高血圧ですが、非感受性の方にも減塩は必要です。なぜなら長年の塩分過多は腎臓に過度の負担をかけ、体液量の増加につながるためです。また、減塩は、降圧剤の効果を良くする、脳卒中や心不全、腎不全などのリスクを減らす効果があります。
厚労省の発表では日本人の塩分摂取量は平均10g以上です。高血圧患者では、医療者から1日6g以下の指示を受けます。
さて、②減塩できない理由は何でしょうか? 問題は、1日何g塩分を摂取しているかを患者が知ることが困難だからです。
栄養指導で食塩摂取量を推定することは重要ですが、日常診療で定期的に塩分量の聞き取りや24時間蓄尿による塩分排泄量の測定は実際的ではありません。
そこで、当院では「あなたの塩分チェックシート」(高血圧学会作成)の使用と随時尿による尿中食塩排泄量を測定しています。
実際、当院通院中の200名の糖尿病腎症患者に、診察の度に減塩指導と塩分排泄量を測定し1日塩分摂取量を計算した上で、A群:塩分量を告げた群とB群:塩分量を告げない群に分けて比較すると、A群では平均10.4g⇒9.5gへ減少しましたが、B群では効果が不十分で、塩分摂取量を知ることが確実に減塩に繋がる事がわかりました。
今年から食品表示がナトリウムから食塩相当量に変わりました。食品購入の際に是非ご覧ください。体を守るためには、当面「ステイホーム」ですが、長期的には「ソルトリミット」が大切になります。
2020年06月17日 苫小牧民報 掲載