難聴と認知症
横山 雄司
(・苫西耳鼻咽喉科クリニック)
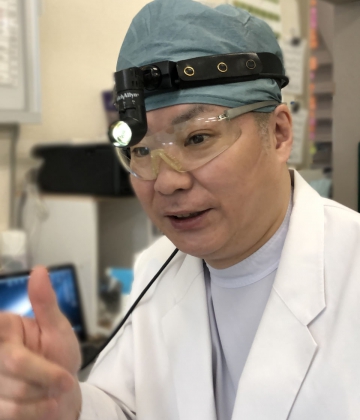
横山 雄司
(・苫西耳鼻咽喉科クリニック)
2019年9月1日現在の総務省統計局発表「人口推計」によると、我が国の高齢化率(人口を占める65歳以上の高齢者の割合)は28.4%であり、すでに2007年から21%を超えた超高齢社会となっています。また、厚生労働省発表の介護が必要となった主原因の構成割合は、平成22年1位脳血管疾患、2位認知症でしたが、平成28年では1位認知症(24.8%)、2位脳血管疾患(18.4%)と、近年は認知症の割合が高くなってきています。
一方で、難聴と認知機能の関連についてはさまざまな研究がされています。2017年のアルツハイマー病協会国際会議において「認知症の約35%は潜在的に修正可能な9つの危険因子に起因する」と言及され、難聴はその予防できる要因の中で最大の危険因子とされました。認知症施策推進総合戦略(2015年厚生労働省)の中でも難聴は認知症の危険因子のひとつで、余暇活動・社会的参加・活発な精神活動等は認知症の防御因子としています。難聴のために言語コミュニケーションが障害されると、会話を避けたり、活動性の低下などにより、抑うつ状態や社会的孤立などに続いて認知機能が低下するとも考えられています。
難聴には耳垢栓塞など治療により改善する疾患もあります。聞こえが悪いと感じたり、健康診断などで聴力低下を指摘されたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。また、加齢性難聴のように改善の難しい場合であっても、適切な補聴器などを用いた聴覚補償によって、聞き取ろうとする負荷の軽減が認知症の予防や発症を遅らせるという指摘もされており、早期に音刺激を増やすことが言語などの脳機能を活性化するとも考えられます。
ただ、少ない刺激に慣れてしまった聴覚に、補聴器で必要音量を伝えると、初めはうるさくてなじまないと感じることがあります。そのため、少なくとも3ヶ月間は常時装用のうえで、音量・音質などを調整するとともに、環境音などの雑音の中から必要な音や言葉を選び取るトレーニングを行うことが推奨されています。さらにはこのことが認知機能の鍛錬にもつながると考えられています。
また、2018年から、補聴器に関する医療費控除制度が発足し、補聴器相談医が発行する「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」など規定の条件をクリアすることで、補聴器購入費用の一定部分は医療費控除の対象となりました。補聴器購入に際しての公的補助の一環といえるでしょう。
言葉は、感情や思考を動かす大切なものです。少しでもきこえが良くなることで、表情がとても豊かになってゆく方を目にすることがあります。聴力において加齢変化からの完全な回復は難しいことですが、適切に補償することは認知機能の低下を抑えることにつながる非常に大切なことと考えています。
2020年03月25日 苫小牧民報 掲載