低音障害型感音難聴とは
山本 潤
(苫小牧市医師会・山本耳鼻咽喉科みみ・はな・のどクリニック)
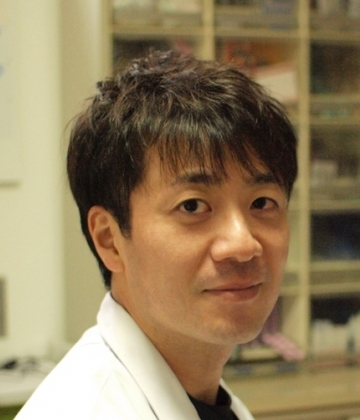
山本 潤
(苫小牧市医師会・山本耳鼻咽喉科みみ・はな・のどクリニック)
■低音障害型感音難聴とは
「低音障害型感音難聴」は、低い音だけが突然きこえにくくなる疾患です。自覚症状としては低い音が聞こえにくい、というより、「耳が詰まった感じ、水が入った感じ(耳閉感)」や、「ゴー・ジーなど低い音の耳鳴り」、「自分の声が響く感じ」を訴えて受診される方が多い印象です。「低音障害型感音難聴」は、メニエール病と同じく、比較的若い女性に多く発症するといわれていましたが、最近は50~60代、あるいはそれ以上の高齢の方にも増えています。低音障害型感音難聴とメニエール病は実は原因は同じで、内耳のリンパ液が過剰となる水ぶくれ(=内リンパ水腫)によって生じます。リンパ液が増える原因ははっきりとはわかっていませんが、体質的なものが多いといわれています。鼓膜の内側は中耳という空間で、中耳のさらに奥に内耳という空間があります。内耳は側頭骨という骨の中に埋まっていて、容積は決まっています。容積の決まった場所にどんどんリンパ液が増えてくると、内耳を栄養している血管が圧迫されて、内耳の血流不足や、神経伝達の障害を生じるといわれています。内耳の中でも聴覚と関係する蝸牛でリンパ液がふえると聞こえが悪くなります。メニエール病では蝸牛だけではなく、平衡感覚と関係する前庭でもリンパ液がふえてめまいをおこします。
■低音障害型感音難聴の原因
上記のように内耳の水ぶくれ(=内リンパ水腫)が原因です。内リンパ水腫は体質的に生じやすいといわれていますが、明確な原因はわかっていません。ただし、睡眠不足、ストレス、体の慢性的な疲れ、風邪などが誘因となるといわれています。
■低音障害型感音難聴の治療法
薬による治療が中心となります。多くの場合、内服治療で改善するため入院は必要ありませんが、難聴が高度である場合や、治療しているにもかかわらず、難聴が進行する場合には、入院が必要になることもあります。
多くの場合、数日から数週間以内で治りますが、中には数か月長引くタイプ、何度も繰り返すタイプもあります。また、この疾患から同じ内リンパ水腫が原因で起こるメニエール病に移行することもあります。
■日常生活の注意点
メニエール病と同じく、疲れやストレス、睡眠不足などが発症の引き金になるので、発症を抑えるには、規則正しい生活、十分な睡眠、ストレス解消を心がけることが大切です。難聴の治療は発症から一週間以内に治療を開始しなければ難聴が固定してしまうこともあります。ですので、耳のつまりや耳鳴り、声が響く感じが続く場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。
2022年10月12日 苫小牧民報 掲載